#17 結婚前夜~『華麗なるギャツビー』/『ジェーン・エア』/『私の男』

マリッジブルーという言葉がありますが、人生の中でも華やかで多幸感にあふれる結婚を前にしても、これでよかったのか、この先何が待っているのかという不安が襲ってくるものなのでしょうか。未婚のわたしは想像するばかりですが、人生に一種の決定打を打ってしまうような、誰かのものになってしまう恐ろしさもあるのかもしれません。文学でも、結婚直前の不確かな感情を描いた文章には心に残るものが多くあります。その先の結婚生活の不幸を暗示したり、より大切な誰かの存在を想像させたり。今回はそんな切り口から三冊を紹介したいと思います。
一冊目は、スコット・フィッツジェラルド『華麗なるギャツビー』です繊細な筆致で1920年代ニューヨークでの恋愛を描いた作品で、アメリカ文学の中でも傑作とされます。
ニューヨークの大邸宅に住む富豪・ギャツビーは毎週豪華なパーティーを開いていましたが、それは実は5年前に離れた元恋人のデイジーと再会するというささやかな目的のためでした。連夜のパーティーは功を奏し、二人は再び会うことになりましたが、デイジーはギャツビーに好意を持ちつつもすでにブキャナンという男と結婚していました。デイジーとの失われた時間を取り戻せると信じて彼女に近づくギャツビー、デイジーの影で浮気をするブキャナン、語り手の青年ニックとデイジーの友達でテニス選手のジョーダン、彼ら感情が交錯した末にある決定的な事件が起こります。
「狂騒の20年代」と呼ばれた1920年代のアメリカだけあってギャツビーのパーティーは素晴らしく贅を極めた狂乱の様相です。しかし、ギャツビー本人は騒ぎまわることなくあくまでも紳士的で社交的に振舞います。
On week-ends his Rolls-Royce became an omnibus, bearing parties to and from the city between nine in the morning and long past midnight, while his station wagon scampered like a brisk yellow bug to meet all trains. And on Mondays eight servants, including an extra gardener, toiled all day with mops and scrubbing-brushes and hammers and garden-shears, repairing the ravages of the night before.
Every Friday five crates of oranges and lemons arrived from a fruiterer in New York-every Monday these same oranges and lemons left his back door in a pyramid of pulpless halves.
週末になると、ロールスロイスは朝の九時から真夜中まで、ニューヨークとの間を行き来して客人を運ぶ送迎バスになった。彼のベンツはすばしこく黄色い甲虫のように走り回り、皆を迎えた。月曜日には手伝いの庭師を含めて八人の使用人が、モップやデッキブラシや金づちや高枝鋏を手に、一日中駆けまわって前の晩の狼藉の後始末をした。
金曜日には毎週、ニューヨークの果物店からオレンジやレモンが五籠届けられ、月曜日には半分に切って中身をくりぬかれた皮が山をなして裏口から運び出された。
この後、デイジーとの関係が近づくにつれ、富豪としての彼の生活にも影が差しはじめます。たった一人の女性との再会を願って、どこの者ともわからない客と夜な夜な酔い明かすパーティーを催していたところには類まれなひた向きさがあります。
デイジーの方も、別れたギャツビーのことを忘れられないまま、社交界では何食わぬふりを装って注目をほしいままにしていましたが、人生の安定や指針が欲しくてブキャナンとの結婚を選びます。下の様子は、デイジーの結婚前夜に取り乱していた様子を友達のジョーダンが後に思い出して語るところです。悲しくてとても好きな描写。
I was a bridesmaid. I came into her room half an hour before the bridal dinner, and found her lying on her bed as lovely as a June night in her flowered dress- and as drunk as a monkey. She had a bottle of Sauterne in one hand and a letter in another.
''Gratulate me,' she muttered. 'Never had a drink before, but oh how I do enjoy it.'
'What is the matter, Daisy?'
I was scared, I can tell you: I'd never seen a girl like that before.
'Here, deares'.' She groped around in a waste-basket the had with her on the bed and pulled out the string of pearls.
'Take 'em downstairs and give 'em back to whoever they belong to. Tell 'em all Daisy's change' her mine. Say, : "Daisy's change' her mine!"'
She began to cry- she cried and cried. I rushed out and found her mother's maid and we locked the door and got her into a cold bath. She wouldn't let go of the letter. She took it into the tub with her and squeezed it up in a wet ball, and only let it leave it in the soap-dish when she saw that it was coming to pieces like snow.
But she didn't say another word. We gave her spirits of ammonia and put ice on her forehead and hooked her back into her dress, and half an hour later, when we walked out of the room, the pearls were around her neck and the incident was over. Next day at five o'clock she married Tom Buchanan without so much as a shiver, and started off on a three months' trip to the South Seas.
私は花嫁のつき添い役だった。婚姻の晩餐が始まる半時間くらい前に部屋をのぞくと、あの子は花柄のドレスを纏って、六月の宵みたいに可憐な姿で横たわっていた。お猿さんみたいに酔っぱらっていた。片手にソールテーヌの白ワイン瓶、もう片方の手に一通の手紙を持っていた。
「お祝いしてよ」あの子はぼやいた。「お酒って初めて飲んだけれど、とっても美味しいのね」「デイジー、どうしちゃったの?」
私は恐ろしくなった。女の子がこんな風に酔うのを見たことがなかった。
「ちょっと、いい子だから」
デイジーはベッドの上にまで持っていっていたくず籠をあさって真珠のネックレスを引っ張り出すと、
「こんなもの、下にもっていって、誰でもふさわし人に返してきてよ。みんなに、デイジーは気が変わったって言って。デイジーは、気が変わったって!」
あの子は泣き始めると、泣いて泣いて、泣き続けた。私はデイジーの母親のメイド急いでを呼んで来て、彼女を冷たいお風呂に入れた。デイジーは手紙を離そうとしなかった。お風呂の中で濡れた紙玉になるまで握りしめ、雪片のようにほぐれるようになってようやく、石鹸置きの上に手放した。デイジーはそれ以上ひと言も喋らなかった。私たちはアンモニア薬を飲ませ、額に氷をあてて元の衣裳を着せ直した。そして半時間後、部屋を後にした時、彼女の首もとには真珠がさがり、騒動は終わったのだった。次の日の5時にデイジーは顔色ひとつ変えることなくトム・ブキャナンと結婚し、南洋へ3か月の新婚旅行に旅立った。
高価な真珠をごみ箱に捨て、慣れないお酒に酔った花嫁が子供っぽい粗野な言葉遣いで「結婚はなしにする」と駄々をこねる。ギャツビーから届いた手紙はデイジーが話すことなく握り続けたせいで湯船に濡れて雪のようにふやけてしまう。
フィッツジェラルドの文体の印象は、秋の陽だまりの中で誰も動かない、声も出さない、セピア色の色彩の中で小さな埃粒が舞うのを息を潜めて見つめているような。決して華美ではないのに肖像画みたいに美しい、そして流れるような展開が見事だなと思います。
この作品は映画化もされていますが、アール・デコのようなコントラストの強い色彩を多用した2013年版よりも、淡い瑪瑙色とクリーム色が支配する1974年版が原作のテイストに近いのかなと思います。長い作品ではないので、ぜひ読んでみてくださいね。

二冊目は英国文学の傑作に数えられる、シャーロット・ブロンテ作『ジェイン・エア』です。人一倍強情で、頭を使って人を観察するのが得意なジェインが、雇い主のロチェスター氏と恋をするお話です。メロドラマチックかというとそうではなく、ジェインは自律心の強く、時に烈しい感情を表現することを躊躇わない人物として描かれます。自らの身に起こったことに関して自ら決断し、道を開いていく強さがあります。ラストでは愛の形について考えさせられ、なんだか神聖な心静かな気持ちになりました。
幼いころに両親を亡くしたジェーン・エアは、癇癪持ちで自分が正しいと思うことを厭わずに指摘する性質のせいで親戚の伯母一家でも、寄宿学校でも、大人たちからは疎まれがちな子供でした。卒業したジェインは外の世界を見たいと言って、ソーンフィールド・ホールというお屋敷で家庭教師をはじめます。
屋敷の主であるロチェスター氏は人に裏切られた過去やみずからの容姿への引け目から気難しい性格をしていましたが、物事を深く洞察し雇い主にも物怖じしないジェインと互いに理解を深めるようになります。
’In about a month I hope to be a bridegroom', continued Mr Rochester; 'and in the interim, I shall myself look out for employment and an asylum for you'.
'Thank you, sir: I am sorry to give―'
’Oh, no need to apologize! I consider that when a dependent does her duty well as you have done yours, she has a sort of claim upon her employer for any little assistance he can conveniently render her; indeed, I have already, through my future mother-in-law, heard of a place that I think will suit: it is to undertake the education of the five daughters of Mrs Dionysius O'Gall of Bitternuttt Lodge, Connaught, Ireland. You'll like Ireland, I think: they're such warm-hearted people there, they say'.
'It's a long way off, sir'.
'No matter- a girl of your sense will not object to the voyage or the distance'.
'Not the voyage but the distance: and then the sea is the barrier―'
'From what, Jane?'
'From England and from Thornfield: and―'
'Well?'
'From you, sir'.
I said this almost involuntarily, and with as little sanction of free will, my tears gushed out.
「あとひと月もしたら、わたしは花婿になる」とロチェスター様が言葉をついた。
「それまでに、勤め口と落ち着き先は探してあげよう」
「ありがとうございます。申しわけもございません、こんなことを―」
「なにも詫びることはない! 雇われているものが、君のように立派に責任を果たしているならば、雇い主が多少の援助をあたえるのは当然だと思う。わたしはすでに、義母になるひとから、君に適当だと思われる勤め口があると聞いている。アイルランドのコンノート州はビターナッツ荘のダイニアシアス・オゴール夫人に五人の令嬢がおり、その教育にあたってもらいたいという話でね。アイルランドは気っと気に入るよ。あちらの連中は人情に厚いそうだから」
「遠いところですね」
「いいじゃないか―君のようにしっかりしている子なら、船旅や距離など意に介すまい」
「船旅ではなく、距離の方が。海に隔てられていますし―」
「なにから隔てられていると言うの、ジェイン?」
「イングランドから、ソーンフィールドから、そして―」
「そして?」
「あなたからです」
私は思わずそう口走っていた。そして知らず知らず涙があふれてきた。
聞いている方が怯むほどまっすぐに気持ちをぶつけるジェインは、純粋すぎて痛々しくも感じられます。こうして二人は結婚の約束をし、婚姻の日を迎えるのですが、この後に試練が待っているのでした。結婚前夜、ジェインは恐ろしい夢を見たと訴えます。
'I dreamt another dream, sir: that Thornfield Hall was a dreary ruin, the retreat of bats and owls. I thought that of all the safety front noting remained but a shell-like wall, very high and very fragile-looking. I wandered, on a moonlight night, through the grass-grown enclosure within: here I stumbled over a marble hearth, and there over a fallen fragment of cornice. Wrapped up in a shawl, I still carried the unknown little child: I might not lay it down anywhere, however tired my arms-however much its weight impeded my progress, I must retain it.'
「もう一つ別の夢を見たのです。ソーンフィールド・ホールが恐ろしい廃墟になり蝙蝠や梟(ふくろう)のねぐらになっているのです。あの堂々とした正面のたたずまいは消え失せ、抜け殻のような壁だけが、とても高く、今にも崩れ落ちそうに見えました。月夜の晩に、わたくしは草がぼうぼうと生えた敷地を歩いておりました。大理石の暖炉につまずくかと思えば、建物の軒飾りの葉片につまずきます。わたくしは肩かけに包んだ、あの見知らぬ子供を抱えています。腕がどれほど疲れようと、その子をどこにも横たえることはかないません。(略)」
ジェインの感情の吐露は、他の人に自分の考えを納得させようとか、思い知らせようという論理的な策略によるのではなくて、ただただ熱く激しい感情が、本人の制御もきかないような次元で強力な精霊になって飛び出しているように思えます。ところどころに幽霊や魂などスピリチュアルな存在の力を思わせる表現が登場するのも特徴です。全身全霊の感情表現と言うのか、ジェイン自身の感情表現にも乗り移りやシャーマンを思わせる側面があると感じました。
'Did you see her face?'
'Not at first. But presently she took my veil from its place: she held it up, gazed at it long, and then, she threw it over her own head, and turned to the mirror. At that moment I saw the reflection of the visage and features quite distinctly in the dark oblong glass.'
'And how were they?'
'Fearful and ghastly to me-oh, sir, I never saw a face like it! It was a discoloured face- it was a savage face. I wish I could forget the roll of the red eyes and the fearful blackened inflation of the lineaments!'
(.......)
'Ah! -what did it do?'
'Sir, it removed my veil from its gaunt head, rent it in two parts, and flinging both on the floor, trampled on them.'
「顔を見たのか?」
「はじめは見えませんでした。でもその女はやがてヴェールを手に取りました。それを掲げて長いことじっと見つめていましたが、やおらそれを自分の頭にかけて、鏡のほうを向きました。その瞬間わたくしは、暗い楕円形の鏡にはっきりと映っているその顔を、目鼻だちを見たのです」
「どんな顔だった?」
「ぞっとするような恐ろしい顔でした―ああ、あんな顔は見たこともありません!色変わりした、獰猛な顔でした。ぎょろりとむいた赤い目と黒ずんで膨れあがったものすごいあの顔を忘れられたら忘れたいのです!」
(中略)
「ああ! そいつはなにをした?」
「ぞっとするような頭からヴェールを取り、二つに引き裂いて床に投げすてると、足で踏みにじったのです」
このお話は、主人公の腐野花が結婚するところから始まり、章ごとに時間をさかのぼっていくつくりになっています。読み進むにつれて、花と養父の淳悟がたどってきた過去が明らかになる。その前段として、どこか幸せに染まりきらない結婚式の模様が、描かれます。
「先日、電話でもお願いしたんですけど、結婚するときに花嫁が、家に伝わる古いもの、門出にふさわしい新しいもの、幸せな人から借りたもの、青いものの四つを身につけると演技がいいらしいんです。サムシングフォーって言うんですけど。まぁ、日本の風習じゃないけど、ロマンチックですからね」
「……ロマンチック」
わたしの口元をみつめながら、淳悟が笑いを抑えるような震え声で返事をした。美郎は目を輝かせて話し続けた。
「えぇ。花嫁にとって特別な人なんだから、お義父さんからなにかもらえたらいいねと、花と相談したんです。なんだか直前でばたばたしていて、申しわけないんですけど。なにしろ披露宴の準備というものが、予想外に忙しくて。親類にも仕事関係にも気を使うし、花は細かいことには興味がなさそうだし」
「サムシングオールド、サムシングニュー、サムシングボロゥ、サムシングブルー、と言うのよね」
(中略)
淳悟がわたしの耳に、薄い、かわいた唇を近づけてきた。
低い声。若いころにはなかったことだが、すこし、しゃがれている。声にはどこか酷薄な響きがあった。
「……サムシングオールド。なんだそりゃ、くだらねぇな、と思ったけど、ちゃんと持ってきた。これだよ」
スーツのポケットに手を入れ、無造作になにかを取りだして、乱暴に投げた。テーブルに、ごろり、と銀色をした四角いものが転がった。ふるびた小型カメラだった。「フィルムも入ったままだよ。花」とつぶやく低い声にあわせて、わたしは短い悲鳴を漏らした。
「淳悟……。あなた、そんなもの、まだ持ってたの!」
養父らはいったい誰が、わたしからあふれるものを、奪ってくれるのだろう……。答える声はなくて、ただきらめく波だけが寄せては返すばかりだった。
それから、観光を楽しんでいるときも、コテージにいるときも、美郎は楽しそうで、穏やかな時間が過ぎた。一度、父親に電話をした時だけすこし緊張していたようだったけれど、電話を切るとまた、楽しそうに翌日の予定を相談し始めた。時間が過ぎるのはのろのろと遅かった。
(中略)「南太平洋って」
エメラルド色に輝く、眩しい海を眺めながら、わたしはつぶやいた。美郎が「えっ」と振りむいた。
「南太平洋って、この世の楽園とか、みんな褒めるけれど。たしかにきれいだし、すごく素敵だけど」
「うん」
「でもどことなく、ばかみたいな海よね」
「えぇーっ」
自分でも知らないうちに、わたしはまた、淳悟がやっていたような、片頬をゆがませた肥育な笑みを浮かべていた。美郎が不思議そうに問いかえした。
「……花、この海を、どこの海とくらべてるの?」

花の記憶にあるのは、オホーツクの凍てつく海。それに比べて「ばかみたい」と言っているのは、悩みとは無縁な南太平洋の海と、無神経なほど能天気な新郎かもしれません。二人の過去に踏み込んでいく序章として描かれるうすら寒い「結婚」の姿でした。
皆さんも、自分に重なる感情がありましたか。メランコリックな花嫁というのは儚くて書き甲斐のある題材だとは思いますが、ジューンブライドの季節にかぶるとちょっと不吉で申し訳ないので、取り急ぎ五月中にお届けしました…。今日も読んでくださって、ありがとうございます。
#16 時間から逃げ出す~『モモ』/『酔え!』/『悩みはイバラのようにふりそそぐ』

忙しくて時間がない、時間に追いかけられる日々から脱出したい。と思うこともしばしばな、せわしない現代です。お休みの日くらいは時間をわすれて羽を伸ばそうとするけれど、時間に捉われないように努力するというのも、つまりは時間を有効に使おう、なるべく無駄をなくそうなんていう時間基準の価値観の搦め手からは逃れられていないわけで。これはもう令和人の末期症状かも知れない。
今日は、なんとかそんな時間の呪いから逃げ出すための魔法を探ってみたいと思います。一冊目は、児童文学の名作、ミヒャエル・エンデ作『モモ』です。コロナ禍が始まってから、時間の使い方を見直す人が増え、この本の売り上げも上がったと聞きました。
円形劇場に一人で住む身寄りのない少女モモは、人の話を聞くことが得意。モモに話を聞いてもらうと誰でも、不思議と心がやわらかくなり、想像力は膨らみ、本当の想いを語ってしまうのでした。モモが特別親しかった二人の友達は、道路掃除夫の寡黙なおじいさん・ベッポと、話し上手な観光ガイドの若者・ジジでした。全く異なる二人でしたが、それぞれモモのことを大切に思っていました。
道路掃除夫のベッポは何事も休み休み時間をかけて考え、行動に移します。道路を掃くにも、「ひとあしすすんではひと呼吸し、ひと呼吸してはほうきでひと掃き」というペースで進めます。そのこころをモモに語っている場面を引用します。
「とっても長い道路をうけもつことがあるんだ。おっそろしく長くて、これじゃとてもやりきれない、こう思ってしまう。」
しばらく口をつぐんで、じっとまえのほうを見ていますが、やがてまたつづけます。
「そこでせかせかと働きだす。どんどんスピードをあげてゆく。ときどき目をあげて見るんだが、いつ見てものこりの道路はちっともへっていない。だからもっとすごいいきおいで働きまくる。心配でたまらないんだ。そしてしまいには息がきれて、動けなくなってしまう。道路はまだのこっているのにな。どういうやり方は、いかんのだ。」
ここでしばらく考えこみます。それからようやく、さきをつづけます。
「いちどに道路ぜんぶのことを考えてはいかん、わかるかな つぎの一歩のことだけ、つぎのひと呼吸のことだけ、つぎのひと掃きのことだけを考えるんだ。いつもただつぎのことだけをな。」
またひと休みして、考えこみ、それから、
「するとたのしくなってくる。これがだいじなんだな、たのしければ、仕事がうまくはかどる。こういうふうにやらにゃあだめなんだ。」
そしてまたまた長い休みをとってから、
「ひょっと気がついたときには、一歩一歩すすんできた道路がぜんぶおわっとる。どうやってやりとげたかは、じぶんでもわからんし、息もきれてない。」
不思議なのは、一歩一歩の今に集中して掃き進めた時の方が、焦って進めた時よりもうまく仕事がはかどっているところ、そして「ひと足、ひと呼吸、ひと掃き」の方法で「どうやってやりとげたかは、じぶんでもわからない」というところです。
「長い時間の流れの中のちっぽけな今」という文脈づけをするのではなくて、「ただ、目の前にある今」に集中することが、時間の呪縛からのがれる一歩目なのかもしれません。
平和だったモモたちの世界ですが、ある時、時間どろぼうである「灰色の男たち」が現れたことで状況はかわります。花を飾ったり、おしゃべりをしたり、インコを飼ったりと日々好きなことをして有意義に時間をすごしていた人々に、灰色の男たちは無駄なことをやめて時間を節約するようにそそのかします。はじめはおかしいと感じていた人たちも段々と時間の節約が幸福への鍵なのだと、思い込み始めてしまいます。
フージー氏とおなじことが、すでに大都会のおおぜいの人におこっていました。そして、いわゆる「時間節約」をはじめる人の数は日ごとにふえてゆきました。その数がふえればふえるほど、ほんとうはやりたくないが、そうするよりしかたないという人も、それに調子を合わせるようになりました。
毎日、毎日、ラジオもテレビも新聞も、時間のかからない新しい文明の利器のよさを強調し、ほめたたえました。こういう文明の利器こそ、人間が将来「ほんとうの生活」ができるようになるための時間のゆとりを生んでくれる、というのです。ビルの壁面にも、広告塔にも、ありとあらゆるバラ色の未来を描いたポスターがはりつけられました。絵の下には、つぎのような電光文字がかがやいていました。時間節約こそ幸福への道!
あるいは
時間節約をしてこそ未来がある!
あるいは
きみの生活をゆたかにするために―
時間を節約しよう!
耳の痛いスローガンですが、「何事も速く無駄なく効率的に」がモットーになった近代以降の価値観に、わたしたちの生活スタイルや行動、さらに幸福に関する考え方がどれほど影響されてきたのかを考えさせられます。
このあとモモは仲間と共に時間どろぼうから時間を取り戻そうと奮闘するのですが、上記の引用箇所のほかにもたくさんの暗示的な、ぐさりと本質を言い当てる言葉たちが散りばめられていて、大人になって今こそはっとさせられます。今一度手に取りたい本だと思います。
次に紹介するのは酔え!(Enivrez-vous)』という詩です。『悪の華』で知られるフランスの詩人・ボードレールの『パリの憂鬱(Spleen de Paris)』という詩集に収録されています。
短い詩なので、原文を交えながら読んでいきたいと思います。
Il faut être toujours ivre. Tout est là: c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du Temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve.
Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous.常に酔っていることが肝要だ。すべてはそこにある。これこそ唯一の問題なのだ。君の肩に食い込み、君を地面に向かって傾けさせる時の重荷を感ぜずにいるためには、休みなく酔っていなければならぬ。
では何で酔うのか?ワインでも、詩でも、勇気でも、君の好きなもので酔うがよい。とにかく酔っているのだ。
『時』を表すTempsが大文字で始まっており、「時間というもの」というような意味になるそう。肩へ食い込み、地面に傾けさせるのが『時』の働きだとすると、『酔い』の効果はその重荷から解き放ち天に向けて上昇する方向性を持っていると感じられます。『時』を忘れるために自分を酔わせるのは、ワインでもいいし詩でもいいし、勇気でもいい。

Et si quelquefois, sur les marches d’un palais, sur l’herbe verte d’un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l’ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l’étoile, à l’oiseau, à l’horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est ; et le vent, la vague, l’étoile, l’oiseau, l’horloge, vous répondront : « Il est l’heure de s’enivrer ! Pour n’être pas les esclaves martyrisés du Temps, enivrez-vous ; enivrez-vous sans cesse ! De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. »
もしも時折、宮殿の階段の途中で、土手の草の上で、陰鬱で孤独な部屋のなかで、君が覚めたときに酔いが消えつつあるとしたら、風に向かって、波に向かって、星に向かって、鳥に向かって、時計に向かって、すなわちすべての逃げ行くもの、すべてのうなりたてるもの、すべての旋回するもの、すべての歌うもの、すべてのしゃべるものに向かって問いかけてみたまえ、“今は何時だ”と。すると風や波や星や鳥や時計らは、君にこう答えるだろう。“酔うべきときだ”と。時に虐げられた奴隷にならないために、酔っていたまえ。間断なく酔っていたまえ。ワインでも、詩でも、あるいは勇気でも、君の好きなもので。
ちょっと可笑しいと思ったのが、他の調度品に交じって「柱時計」までもが同調していること。「あなたくらい役目通り、時刻を答えたらどうなの」と言いたくなるけれどそれもご愛嬌かな。
ボードレールは「酔い」は飲酒に限らず「美徳」や「詩」でもいいと言います。時間や我を忘れて没頭し、没入することを言っているのだと思われます。お酒の勢いに任せて社会規範なんて忘れてしまえ、と主張しているのではなく、自分の立場や常識を忘れさせる没頭こそが想像の源になり、凝り固まった思想や常識(=時間!)、それに時間や論理から導き出される必然性や因果関係、前後関係から解放してくれるということなのではないかと思います。それはどこか、「前後から切り離された、ただ今という時間」を大切にするベッポの論理にも通じるところがあるように思えます。
締めくくりには、詩の一部と短歌を少し引用したいと思います。
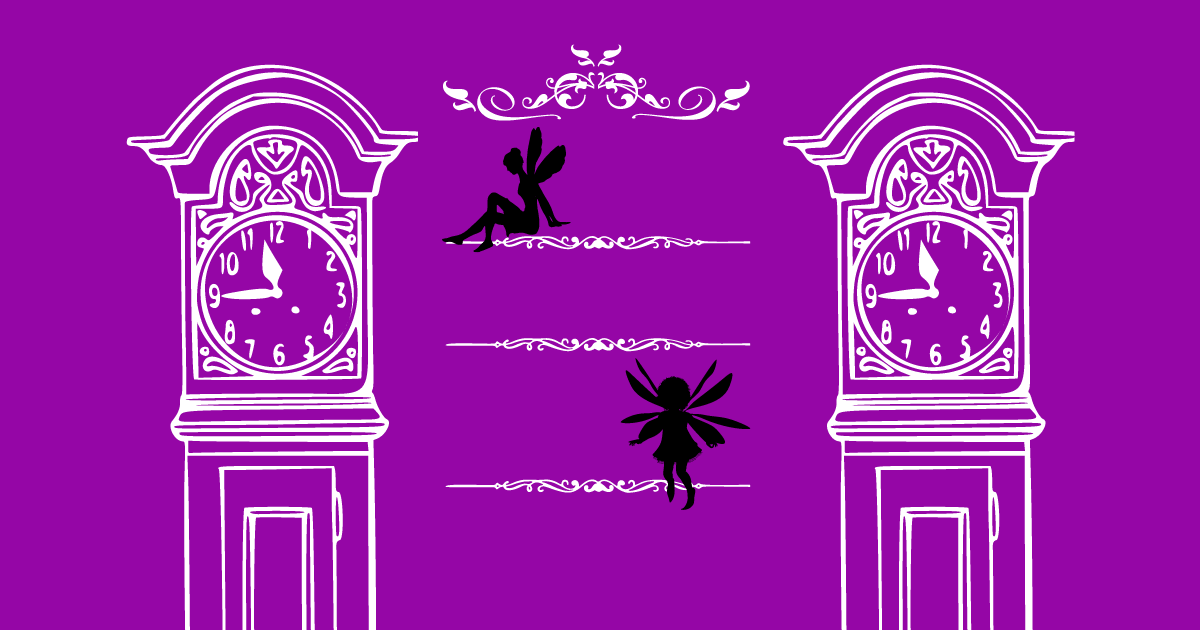
以前にも引用した俵万智さんの『短歌をよむ』に取り上げられていた山田かまちさんの作品から、時間について書かれた一節。山田かまちさんは10代の頃に制作した詩や絵や文章を数多く残して、1977年に17歳で逝去した詩人・画家です。作品には高校生の年齢の若者に押しつけられる価値観への反抗や、自分が何者かという葛藤が生の言葉と感情で吐露されています。その中でも、俵さんが注目していた部分がこちら。
ぼくは感じた
忙しさとねむさのなかで。
「そうだよ! なぜもっと早く
気づかなかったんだろう!」
そこでぼくは時間に質問した。
「君はまじめすぎるじゃないか、
なんでもっと気楽に遊べないの?」
なんだってんだい!
ここまで、時間め!
ついてこなくたっていいだろう!
それより答えろ
ぼくの質問に。
その時やってきたんだ、
まただよ。
ねむけと忙しさ。
(以下略)
俵さんもこれを読んで、短歌を詠んでいます。
教室のでかい時計の上をゆくおまえは真面目すぎるよ、時間
子供の時、高校生の時、そして大人になった今を振り返ると、時間の進み方や主導権が違うような気もします。幼い頃は時間は無限にあっていくら遊んでも海水のように減ることがなかった。それがいつからか巧く使うべき資本となり、同じ時間のなかでの効率や進捗を気にするようになった。灰色の男たちの思想が今はすっかり内在化されてしまっている危機感もあります。
わたしはまだ読めていないのですが、山田かまちさんの遺作の絵画や詩をまとめて出版されたものが『悩みはイバラのようにふりそそぐ:山田かまち詩画集』です。1992年の出版当時、大きな反響があったそうです。表紙の絵柄からも原色を使った強い表現やぼかしたような塗り方の特徴がうかがえます。
「時間から逃げ出す」をテーマに三冊を取り上げましたが、いかがでしたか。時間のとらえ方が変わると、不思議なことに、生活や人生、幸福へのとらえかたも変わってくる気がします。少しでも、時間にがんじがらめにされた毎日を組み直すヒントになれば。
最後まで読んでくださって、ありがとうございます。
#15 今、よみたい本~『となり町戦争』/『服従』/『The Journey』

今回は『今、よみたい本』という題で、2022年の立ち位置を考える本を二冊、紹介したいと思います。そのうち収まるのかなと楽観視していたコロナは依然として猛威を振るい、将来は暗雲に包まれている。その一方で、昨年になってアメリカのトランプ政権が集結し、2015年ごろに盛り上がった保護主義的な流れも答え合わせというか決算というか、ある程度の動きを振りかえる時期に来ている。ここまでとここからの数年間を見据える、2022年の読書のお供に。
ここに来て強烈に感じるのは「分断」が色濃くなっていること。コロナが広まった当初は「病気は人を差別しない」と思われたのに、結局は経済力によってどんな治療が受けられるか、感染機会をどれだけ避けられるかに差が生まれる厳しい現実を目の当たりにしている。ステイホームを楽しもう、という積極的な流れも目新しさを失って、閉塞感と孤独感が際立っている。開放的なパーティーを開く奔放な他人を見つけようものなら、羨ましさと正義感と感染恐怖のない交ぜになった無慈悲な攻撃性を発揮せずにはいられない、近頃の世のなか。一度立ち止まって、社会をこんなにも苦しめているものの正体を、ちょっと静かに観察してみたい。
一冊目は、三崎亜記さんの『となり町戦争』。不可解な設定ながら、それが現実 象徴的な ありありと現実に染み込んでくる印象を与える本だと思います。
わたしの手元にある集英社文庫の背面に書いてある、あらすじはこちら。
ある日突然にとなり町との戦争がはじまった。だが、銃声も聞こえず、目に見える流血もなく、人々は平穏な日常を送っていた。それでも、町の広報誌に発表される戦死者の数は静かに増え続ける。そんな戦争に現実感を抱けずにいた「僕」に、町役場から一通の任命書が届いた……。

この本をめくっていて気づくのが、ところどころに町役場の行政的なフォームが挿入されていること。例えば、開戦を告げる町の広報誌の記事は、町内のお祭りの開催を知らせるかのように、こんなフォーマットに載せて書かれています(本物は、これがさらに二重線の四角で囲んであり、いかにも区役所や市役所の使いそうな形式)。
【となり町との戦争のお知らせ】
開戦日 九月一日
終戦日 三月三十一日(予定)
開催地 町内各所
内容 拠点防衛 夜間攻撃
敵地偵察 白兵戦
お問い合わせ 総務課となり町戦争係
他にも、私物移動リストや戦争参加の任命書類が、よく見る形の書類フォーマットに収まって淡々と処理されていく。リアリティを伴ってこない「戦争」の実体に対して、これが「平穏」の形なのか、不思議な形で日常が延長しているから、この書類の先に人の命が左右される事態があるなんて、つくりごとに思えてくる。それでも自分の認知する外側で大切な物が奪われている現実がある。
僕は混乱していた。あの夜、僕は香西さんの指示どおりに逃げ回りながらも、何だかスパイ映画のようなスリルと興奮をあじわってさえいたのだ。そんな僕を逃がすために、佐々木さんの命が犠牲になったということが、理解できなかった。(中略)
「わからない、ぼくにはあいかわらずよくわからない。人が一人死んだ。ぼくのために。戦争の意味がまったくわからない。ぼくがスパイ映画気取りで逃げまわっていた間に……。でもそのことへの罪悪感がまったくわいてこない。あまりにもリアルじゃないから。まるで遠い砂漠の国で起こった戦争で、死者何百人ってニュースで聞いてるみたいだ。(略)」
続く部分も引用してみます。不可解な状況ながら、暗にわたしたちののうのうとした日常の本質をあぶり出すようで、はっとします。
「僕の目に見えるもの、見えないもの」に想いをはせた。香西さんが涙を流しているその「何か」を見極めようとした。香西さんも、今この戦争の中で何かを失おうとしているのかもしれない。僕は香西さんの、「失われゆくものに流された涙」をそっと口にふくんだ。夢の中の海の水とは違い、それはきちんと涙の味として、僕の一部となった。その涙の味だけが、今の僕にとってのリアルだった。
傍らで確実に起こっている人の死や戦争、苦しみとパラレルな世界で何事もなく進行する日常が怖くもあり、それが実状だと思う部分もあり。他人への無頓着、無関心、それに自覚しながらの看過が描かれていて、突飛な設定ながらも考えさせられることが多い小説です。「リアル」と「リアリティ」。「現実・実状」と「実感・現実感」。必ずしも連動しないからこそ、想像力を持たなければと思います。
二冊目はもう少し政治色が強いのだけれど、2016年ごろに世界中で大きな話題を空き起こしたミシェル・ウエルベックの『服従』。ウエルベックはフランスの作家・詩人です。
この本は2015年の発売当初、世界中を議論に巻き込み飛ぶように売れました。アメリカでは自国優先の姿勢を取るトランプ政権が誕生し、フランスではマリーヌ・ルペン率いる極右政党の国民戦線が選挙でかつてないほど議席を伸ばした頃。イスラム国の台頭やテロの多発、移民問題の拗れから先進国にだんだんと保護主義の色が濃くなっていっていました。『服従』は、2022年のフランスを舞台として「イスラム教勢力がフランスの政権についた」世界を描きます。ちょうど今頃の話だと思うとどきりとします。小説通りの経過にはならなかったけれど、そのかわり世界はどんな道を選び、今に至ったのか。

この政治的動乱の一方で、主人公の大学教授は自身の存在や仕事に対して虚無感や閉塞感を抱いています。ユイスマンスを研究し博士号を取得したものの、文学の研究の真の価値は社会の中で評価されない。イスラエルに移住するという恋人と別れ、イスラム教をもとにした教育方針に従う同僚の教授や、新しい権力による変革に晒されながら、何が正しいことなのかに揺れ、立ち振る舞いを決められないままでいる。反発する者、受容する者、立ち去る者がいる中で主人公は取り残されて行きます。
周知のことだが、大学の文学研究は、おおよそどこにも人を導かず、せいぜい、最も秀でた学生が大学の文学部で教職に就けるくらいである。それは明らかに滑稽な状況で、突き詰めると自己再生産以外の目的を持たず、有り体に言えば、学生の九五パーセント以上を役立たずに仕立て上げる機能を果たすだけの制度なのだ。(中略)つまり望みさえすれば、ぼくには大学教員になるチャンスがかなりある、ということなったのだ。ぼくの人生は、その単調さと、予測可能な凡庸さにおいて、一世紀半前のユイスマンスのそれに重なり続けていたことになる。
この小説には、現実と地続きになっているような表現が度々登場します。例えば、党首のマリーヌ・ルペンの出で立ちや力強い態度は、ニュースで見て知っている姿から想像されて、あたかも2022年の彼女を描いたものに思われてきます。
マリーヌ・ル・ペンは十二時半に反撃に出た。活発で、ブラシをかけたばかりの髪、パリ市庁舎の前でローアングルで撮られた彼女は、ほとんど美人と言っても良かった。それは彼女がそれまでに姿を現した時とは明白に対比をなしていた。二○一七年の転換期以来、この百パーセントフランス製の候補は、最高官職に達するためには、女性の場合必然的にアンゲラ・メルケルのような雰囲気を醸し出さなければならないのだと確信し、このドイツ首相の重々しい貫禄に匹敵しようと努め、髪型や服装を真似することまでしていたのだ。しかし、この五月の朝、彼女は運動初期を思い起こさせるような、燃え立つ斬新なエネルギーを再び見いだしたようだった。
この小説は、フランス作家のユイスマンスやキリスト教・イスラム教教義に基づいた哲学的・宗教的考察が関わってくるので、特に後半部分は難解だと思います。主人公はもがきながら、社会と距離を置いたり教会を訪ねたりするけれど、大きな流れに逆らう術も、自分の存在価値も見当たらないというような、絶望的な雰囲気が続きます。
最後に引用する部分は、イスラム教の考え方を主人公に説こうとする知人の台詞ですが、宗教的な考察を横に置いてみても、「人間の絶対的な幸福が服従にある」という言葉が非常な重みをもって響きます。博士号も取得し、深く広い知を持っている主人公が、その論理にさからう手立てをもっていないのが、象徴的だともいます。
「『O嬢の物語』にあるのは、服従です。人間の絶対的な幸福が服従にあるということは、それ以前にこれだけの力を持って表明されたことがなかった。それがすべてを反転させる思想なのです。わたしはこの考えをわたしと同じ宗教を信じる人たちに言ったことはありませんでした。冒涜的だと捉えられるだろうと思ったからですが、とにかくわたしにとっては『O嬢の物語』に描かれているように、女性が男性に完全に服従することと、イスラームが目的としているように、人間が神に服従することの間には関係があるのです。お分かりですか、イスラームは世界を受け入れた。そして、世界をその全体において、ニーチェが語るように『あるがままに』受け入れるのです。(略)」

さて、振り返ってみると、「服従」が出版された2015年から2016年にかけてはイスラム国の台頭が世界中を震撼させ、センセーショナルに取り上げられていました。テロに屈しないという決意や、自分も当事者だという共振の思いから、暴力に遭った都市の名を冠した「I am Paris」「I am Brussels」のスローガンを多くの人が掲げました。
あの気運の高まりは、どこへ行ったのだろうと不思議になります。見えやすい、わかりやすい犠牲が表に晒されなくなったからと言って、紛争は終わらないしむしろ事態は悪化しているのに。わたしたちはどこかで惨事に馴れ、リアリティの薄れた物語の向こうに、誰かがいることを忘れがちなのではないかと危機感を覚えます。
ちょっと重い回でしたが、いまと過去と未来を見据えて「分断」を考え直せればと思います。読んでくださってありがとうございました。
~今日のおまけ
『ジャーニー 国境をこえて』(フランチェスカ・サンナ作、訳)という絵本があります。紛争により、家を追われた家族が命を守るために国境を越える旅が描かれています。色彩の豊かな、想像力を刺激する美しい絵なのですが、だからこそ眠っている間に瞼の奥で広がる不安や、見知らぬ土地に放り出される恐怖、終着点の見えない旅の途方のなさをよく表して、心が痛くなります。人々の暮らしがあったということ、今もあるということ。忘れずにいたいと強く思います。
#14 句読点の妙~『春琴抄』/『窓の魚』

こんにちは、久しぶりの記事投稿になりました。今回は、表現からみたテーマに立ち返り、句読点の使い方がちょっと特徴的な二作品を取り上げたいと思います。句読点は意味の区切りや文の終わりをわかりやすく示す役割だけでなく、文章全体のリズムを左右するものだと思います。句読点の特徴によって、文章の持つ音楽性が変わってくることを感じながら、読み進めていきます。
まず一冊目に紹介するのは谷崎潤一郎の『春琴抄』。この小説は、盲目の三味線奏者・春琴と、彼女の弟子でもあり身の回りの世話をする丁稚の佐助の奇怪な愛の形をを描いた作品なのですが、極端に句読点を省いてある点でも特徴的です。文章を読みやすくする役割の読点「、」や「かぎかっこ」がほとんど見られず、句点もないところがあるので文の区切りさえ怪しくなってきます。
その書き方によって、登場人物との間にある冷たい距離を感じるとともに、読経を聞いているような、おどろおどろしさまで感じられてきます。墨書きの草書の経文を聞かされているような、際限ない帯を手繰っているかのような、仏教的な静の感覚の中で物事が進んでいく冷たさを感じるところもあります。
『春琴抄』は、春琴と温井検校の墓の描写から始まります。語り手は、春琴に生涯寄り添った温井検校(幼少期の名は佐助)が彼女のことを記した『鵙屋春琴伝』という読みもとを紐解く形で、二人の奇異な関わりを語っていきます。
大阪の薬屋の娘として生まれた春琴は、美貌ながらも子供の時に失明し、以来三味線や琴といった音楽の道に励みます。稽古へ赴くのも、身の回りの事をするのも佐助という名の丁稚が手伝いました。佐助は奉公人として美しい春琴を心から慕いながら、彼女の目となり手足となって過ごし、春琴も佐助をほかにいない存在として扱いました。春琴は甘やかされたお嬢さんらしく強情で気ままなところがあり、佐助に無理を言うこともしばしばでしたが、佐助はそれを苦にするどころか、春琴が強く当たるのを甘えられているとも捉え、一種の恩寵とまで感じていました。
四人の姉妹のうちで春琴が最も器量よしという評判が高かったのは、たといそれが事実だとしても幾分か彼女の不具を憐れみ惜しむ感情が手伝っていたであろうが、佐助にいあってはそうではなかった。後日佐助は自分の春琴に対する愛が同情や憐
愍(れんびん) から生じたという風に云われることを何よりも厭いそんな観察をする者があると心外千万であるとした。わしはお師匠様のお顔を見てお気の毒とかお可哀そうとか思ったことは一遍もないぞお師匠様に比べると眼明きの方がみじめだぞお師匠様があのご気象とご器量で何で人の憐れみを求められよう佐助どんは可哀そうじゃとかえってわしを憐れんで下すったものじゃ、わしやお前たちは眼鼻が揃っているだけで外の事は何一つお師匠様に及ばぬわしたちの方が片羽ではないかと云った。ただしそれは後の話で佐助は最初燃えるような崇拝の念を胸の奥底に秘めながらまめまめしく仕えていたのであろうまだ恋愛という自覚はなかったであろうし、合っても空いては頑是ないこいさんである上に累代の主家のお嬢様である佐助としてはお供の役を仰せ付かって毎日一緒に道を歩くことの出来るのがせめてもの慰めであっただろう。
注:佐助は春琴を「お師匠様」と呼びます。また、「お嬢さん」という意味で親しく「こいさん」と呼ぶこともあります。
句点がないことで、「主家のお嬢様である佐助としては~」など修飾関係がわからなくなってしまう所があります。その境目のなさが、主従の別、主客の別を曖昧にさせ、春琴と佐助が表裏一体の存在に感じられてくる。

佐助は春琴に気に入られ、彼女に師事して三味線を習い始めますが、気性の激しい春琴の稽古は折檻になることもありました。しかし音曲の稽古という厳しく特別な場を介し、また盲目の主人と手引きをする奉公人として、二人は特別な愛の関係で結ばれてゆきます。結婚こそしませんでしたが二人の仲はだれも疑わないものになりました。
春琴は四十歳を過ぎても、持ち前の美貌を保っていましたが、激しい気性もあり人に憎まれることもありました。ある日、何者かが春琴の屋敷に侵入し彼女に熱湯を浴びせかけるという事件が起きました。春琴は顔に無惨な火傷を負い、人を誰も近くに寄せなくなります。盲目の春琴ですが、自分の姿を確かめられないまま佐助に痛々しく醜い姿を見せるのを嫌がったのか、それを察した佐助は二度と彼女の姿を見ずに済むよう、自らの眼を針で突いて失明するのでした。
程経て春琴が起き出でた頃手さぐりしながら奥の間に行きお師匠様私はめしいになりました。もう一生涯お顔を見ることはござりませぬと彼女の前に額ずいて云った。佐助、それはほんとうか、と春琴は一語を発し長い間黙然と沈思していた佐助はこの世に生れてから後にも先にもこの沈黙の数分間ほど楽しい時を生きたことがなかった昔悪七兵衛景清は頼朝の器量に感じて復讐の念を断じもはや再びこの人の姿を見まいと誓い両眼を抉(えぐ)り取ったと云うそれと同期は異なるけれどもその志の悲壮なことは同じであるそれにしても春琴が彼に求めたものはかくのごときことであったか過日彼女が涙を流して訴えたのは、私がこんな災難に遭った以上お前も盲目になって欲しいという意であったかそこまでは忖度し難いけれども、佐助それはほんとうかと云った短かい一語が佐助の耳には喜びに慄(ふる)えているように聞えた。
春琴抄はある異様で極端な愛の形を描いた作品であり、「マゾヒズム」「窮極の耽美主義」と評されることが一般的です。ですが、文体自体は情熱的にたたみかけたり、烈しい言葉を連ねたり、まして感嘆符!や思わせぶりな…を使うこともなく、ある静けさを保っているのが印象的です。

二冊目、句読点(特に読点「、」)が多い作家として思い浮かんだのが、西加奈子さんです。読んでいる間から度重なる読点のリズムに翻弄され、読み終えたころには脳内の考えごとも「、」ばかりのモノローグに支配されてしまいます。ということで、西さんの作品の中でもわたしの好きな『窓の魚』を紹介します。
舞台は、二組のカップルが一緒に訪れた温泉宿。楽しいはずの旅行なのにトウヤマとハルナ、アキオとナツの四人の間には微妙な不協和音が流れている。表立って反目するわけではないけれど、お湯の中で裸になると互いが匿し持っていた冷徹な慾や自意識が見え隠れする。
しばらくじゃばじゃばやっていると、ナツが急に、湯船に潜った。岩にお湯をかけ始めたり、やっぱり、何を考えているのか分からない。ナツ、と呼んでも、聞こえないのか、一向に出てこない。あんまり長い間そうしているから、不安になって覗き込むと、目を大きく開けて、空を見ている。
「ナツ?」
湯船の中で白い肌が、ますます青白く光っている。ゆらゆらと揺れる髪の毛は、いつもの傲慢な硬さを見せないで、頼りなく、広がっている。
「あんた、死体みたいよ」
そう言ったけど、ナツに聞こえないことは、分かっていた。
「ニャア」
そのとき、猫の鳴き声が聞こえた。どきりとした。見回しても姿が見えなくて、気味が悪かった。
「ニャア」
引用してみると、覚えていたよりも読点が多いというわけではない…。けれど一冊読み終えたころには、言葉のまとまりごとにうなずくようなリズムが身に着いてしまうんですよね。

物語は四人が順に語り手となり、同じ景色や場面を違った方角から語り直す形をとっています。読み進めると、お互いの会話がうまく聴きとれなかったり、意味を取り違えられていたり、見くびっていた相手に見透かされていたりしていたとわかる。四人は言葉レベルで確実にどうしようもなく擦れ違っているけれど、不思議なところで人を信じてみようと思う強い気持ちが現れたりもする。
「……た?」
ハルナが耳元で、何か言った。唇が近すぎて聞こえなかったし、聞く気もなかった。
「……ちゃった?」
ハルナの声は、さっき湯船で、俺に声をかけたアキオの声にそっくりだった。何かを請うような、気色の悪い声に、そっくりだった。
「トウヤマ君」
そのとき、また携帯が鳴った。
「トウヤマ君」
もしかしたら、あいつは俺のことを、好いているのではないか。
それは、願望ではなかった。予感でもないし、ましてや確信でもなかた。ただ、ぶるぶる震えている携帯を見ていると、そう思った。どろどろに酔って、携帯を耳に当てているあいつの姿は、俺の胸をつかんで離さなかった。

人を傷つけてしまいたいという残酷な感情や、自分をぞんざいに扱う歪んだ承認欲求のようなもの、無感動のまま口の端だけ笑う荒んだ気持ち、そんな四人の傍らで美しい女性の死体が見つかる…。同じ日に宿泊していた老婦人の記述はこんな通り。
女の人の死体が浮かんでいたという、あの池の上を、歩いたのだという事実、宿の浴衣が、鯉と一緒に、ゆらゆらと揺れていたのだと思うと、それはひどく、美しい景色のような気がしました。そして、その女の人が、出来るなら、私が露天風呂で会った、あの女の子であればいいと、思いました。
細くて、わずかな翳りがあって、真っ黒い髪が濡れるのもかまわなかった、あの子なら、きっと、橋の下でたゆっているのが似合うわ、とそんな不謹慎なことを、思っていました。
生きている四人の冷たい腹の内が明らかになるなかで、温泉宿の景色も手伝ってその死体の描写が一番綺麗な部分かも知れないと思ってしまいます。
句読点のさじ加減で物語の音程が変わる、語り口のトーンが変わる。ちなみに短歌に句読点を持ち込むのはちょっと邪道なようです。ふつう韻文は韻文の枠組みのなかでリズムを成立させるのが一般的で、句読点は個性的な作風の人が巧く使わなければ作品を損なってしまうような気がします。有名どころでは、折口信夫さん(釈迢空)の短歌がこちらです。
葛の花踏みしだかれて、色あたらし。この山道を行きし人あり
では今回は引用も長くなったので、こんなところで。読んでくださってありがとうございます。
#13 アートのすすめ~『名画を見る眼』/『美術の物語』

芸術の秋ですね。マイナーかもしれませんが、わたしは芸術の中では美術鑑賞が好きです。美術館に行くととてもリフレッシュできるし、他では得られない種類のエネルギーを蓄えられる気がします。今日は、美術の理解を深める本を紹介しながら、絵画鑑賞の布教を行っていきたいと思います! 自然と熱が入っていますが、気楽にお読みください。
といっても、美術鑑賞は難しいもの、堅苦しいものと思われがちです。それに、退屈する人が多いのも確か。よくわからない主題の古い絵を見せられても、何が良いのか困ってしまうことがありますよね。そんな時は、ちょっとした背景知識を入れておくと見方が変わるかもしれません。
一冊目に紹介するのは高階秀爾氏の『名画を見る眼』。絵が描かれた背景やモチーフの意味、画家の人生などについて触れた、もう古典と呼んでいいような有名な一冊です。
世界の名画を個々に紹介しながら、その絵に描かれたモチーフなどについて、詳細に解説しながら見ていくスタイルです。西洋古典美術はキリスト教に根差したアイコンや世界観を表現することが多いのですが、そのあたりの知識を補いながら解説してくれます。また、作者や時代の背景を知ることで見逃しがちな細部にも注目するきっかけを与えてくれます。

たとえばこの夫妻像。フランドルの夫婦を描いた肖像画ですが、この本はまず精緻に描写します。
例えば、画面左手の窓からさしこむ北国らしい鈍い陽の光を受けて輝く真鍮のシャンデリアの硬質な金属的な肌、主人公アルノルフィニの袖なしの長衣を縁どっている毛皮、婦人の頭を覆う白ヴェールのレース飾りなど、思わず手を伸ばして触れてみたくなるほど、なまなましい迫真力を持っている。
それからこの絵に描きこまれた数々の図像の解読へと展開していきます。
ここにはいろいろなシンボル(象徴)が描きこまれている。例えば、(省略)シャンデリアには、蝋燭が一本灯されている。むろんこれは、この場を照らし出すためではない。一本だけ灯された燭台は、中世以来、「婚礼の燭台」と呼ばれて、結婚のシンボルなのである。
あるいは、右手の寝台の奥の壁ぎわに置かれた椅子の背の木彫りの飾りがそうである。これは、両手を合わせた聖女マルガレーテの像であるが、聖女マルガレーテは、子宝を待ち望む女性の守護聖人である。彼女の像が新妻の顔のすぐわきに描かれているのは、決して偶然ではない。
さらに足元の犬は忠節、窓際に無造作に積まれたオレンジはアダムの林檎を想像させて原罪、そして十字架の救いを暗示します。こうして一枚の絵画からその深い背景や宗教的意味まで惹きこまれるように読んでしまうのがこの本の魅力です。
「名画に実は恐ろしい裏物語が…」というようにセンセーショナルな面に注目した書籍もありますが、わたしが「名画を見る眼」に感じるのは一過性の驚愕や衝撃にこだわることなく、静かに深く絵を読み解く姿勢です。文章が上品できれいなので、知識を無理にインプットしているという感覚なく、学ぶことが出来るのも素敵なところです。
高階氏は文庫版の「あとがき」でダヴィンチの言葉を引用し、こう語っています。
レオナルド・ダ・ヴィンチの手記の中に「絵画とは精神的なものだ」という一句がある。この言葉は、さまざまな意味に解釈され得るだろうが、少くともレオナルドが、絵画を単に手先の技術としてのみ捉えず、感覚的、理知的ないっさいのものを含めた全人間的な精神活動と考えていたということは、ほぼたしかであろう。
突き詰めて言えば、絵画を見る側も感覚だけでなく、理知的なもの一切まで含めた精神活動に参加していることになります。ただ見て綺麗だ、繊細だ、不快だというだけでなく、なぜそう感じるのか、作者はそう感じさせるように描いたのか…などと考えるときりがなくなります。
ちょっと雑談になりますが、わたしにとっての美術鑑賞は「思考」と「感覚」をすり合わせる体験なのかな、と感じています。日々の生活や仕事ではどうしても「思考」に重点が偏りがちです。どうすれば効率的に作業を進められるかとか、今の方法で成果が出ているかとか。論理的に、客観的に、筋道立てた思考のパターンに陥ってくるという感じ。
もちろんそれも大切ですが、ずっとその型の中にいると窮屈になってきます。思うがままのフィーリングを受け容れ、もし思考と矛盾してもよしとする。凝り固まってしまった思考パターンを、「感覚」がいとも簡単にひっくり返してくれるのは快感だし、新発見の連続です。世間でもてはやされているはずの絵にあまり惹かれなかったり。全く無名な一枚の前から離れられなくなったり。前評判にも増して心を奪われてしまったり。「頭ごなしの思考」を気持ちよく覆してくれる、「感覚」の反乱なのかなと思っています。これが思考のデトックスなら、美術館に行くことで少しはバランスが良くなるかな。そういう意味での、「すりあわせ」だと考えています。伝わるかな?

二冊目は、『美術の物語』という本。エルンスト・ゴンブリッジ氏という美術研究の大家が、一般向けに執筆した一冊です。この本、実は数年前にポケット版の日本語訳は絶版となってしまっています…。巻頭カラーの図・写真も充実して2000円台とお値打ちだったのですが、今オークションサイトで買おうとすると5000円はくだりません。わたしも友達に借りて読んでいたのですが、買おう買おうと思っているうちに逃してしまいました。今回は図書館で借りてご紹介しています。
この本の特徴は、紀元前から現代にいたるまでの美術史を「物語」のようにひと繋がりの流れとして語っているところです。
美術の様式には時代ごとに傾向やトレンドがあり、ゴシック、ロマネスク…などの名前がついています。(それが美術の敷居を上げているところもありますが、)そのようなスタイルの変遷がある意味歴史のように必然的に、前のものを受けて次のものが生まれる形で移り変わってきたことをとらえることが出来ます。
ゴンブリッジ氏は序文の中で、この本は美術の道案内となる物語として読んでほしいと言った上で、読者についてこう想定しています。
この本を書きながら私がとくに念頭に置いていたのは、美術の世界を自分で発見したばかりの十代の読者だった。しかし、若者向けの本だからと言って、大人向けの者と書き方を変える必要などまったくない。若者こそもっとも厳しい批評家であって、偉そうな言い回しをしたり、わざとらしく感心してみせたりすれば、たちまちソッポを向かれてしまう。
平易な言葉遣いで流れるように綴られているので、次へ次へとページをめくって進みたくなるような本です。

イタリア人を両親にもつギリシャの画家ジョルジョ・デ・キリコ(1898-1967)の野心は、人が思いもかけない絶対の不思議に出会った時、どんな奇怪な感覚に襲われるかを絵にあらわすことだった。彼は、現実を再現する伝統的な表技法をそのまま使って、壮大な古典彫刻の頭部と巨大なゴム手袋を廃墟の都市に並べ、それを《愛の歌》と名づけた。
ベルギーの画家ルネ・マルグリッド(1898-1967)は、この絵の複製を初めて見たときの感想を、のちに、こう書きとめている。「芸術家とは、才能と名人わざと、あれこれちっぽけな美学的特質の虜にすぎない。キリコの絵に示されているのは、其処からの完全な断絶である。そこに新しいヴィジョンが生まれた……」。
時代が前後しますが、美術史の中でわたしが面白いなと思うのは、「盛期ルネッサンス」の次に「マニエリスム」が登場したこと。「ルネッサンス」は三次元的な立体感や奥行きを重視し、いわば一番「現実の目で見るのに近い、リアルな」表現が特徴です。たとえばこんな感じ。

しかし「写実的で構図の完璧な」美術スタイルが確立されても、そこで終わりではありません。次の時代になると、人物の手足や顔を現実ではありえはいほど長く引き伸ばし、誇張して描く「マニエリスム」が発生してきます。

こんな風に、滞ることなく移り変わるのが美術の歴史の興味深いところ。
1520年代、イタリアの美術通たちはみんな、絵画は完成の域に達したと考えたらしい。実際、ミケランジェロやラファエロ、ティツィアーノやレオナルドなどは、画家たちがそれまで目指してきたことを達成してしまったのだった。(中略)実際、同時代の風潮に疑問をもつ若者も少なくなかった。そもそも芸術が行き詰るなんてことがあるのか? なにをやっても前時代の巨匠を超えられないというのは本当なのか?
(中略)彼らはこう言いたかったようだ―たしかに巨匠たちの作品は完璧だ。しかし、完璧なものも時間が経てば飽きられるし、慣れてしまえばインパクトもなくなる。自分たちが目指すのは、人をはっとさせるようなもの、意外なもの、前代未聞のものだ―。
知識と感覚、どちらかだけでは十分に楽しめないと思うから、その二つの相互作用が働いていつもでは湧かない発想や感情が生まれる絵画鑑賞。好き勝手書きましたが、絵画の楽しみ方は人それぞれです。興味が湧いてきたら、深いことを考えずにふらりとギャラリーへ足を運んでみるのがおすすめです。今日も読んでくださってありがとうございました。
~今日のおまけ
わたしが全力でおすすめする子供向けアート絵本「小学館あーとぶっく」シリーズ。堅苦しいことなしに、色や形の面白さを感覚でとらえることを教えてくれます。それから、ところどころ「なぜだと思う?」と問いかけてくるのも魅力。モネの積みわらを色塗りしたり、マティスの切り絵に挑戦してみたりするうちに、美術が好きになるはず!
蛇足:今年、美術検定の2級を受けてみようと思います!
#12 書く者の心構え~『山月記』/『The Shadowland of Dreams』/『文学と自分』

久しぶりに高校の教科書を開く機会があって、ぺらぺらとページをめくるうち、中島敦作の『山月記』が目に留まりました。優秀な官吏でありながらも詩人になることを志して隠居した李徴が、自分自身と周囲の人に対するプライドに苛まれた挙句、虎に姿を変えてしまう話。みなさんも覚えがあるかもしれません。
高校生の当時は、「李徴はひどく自意識の強い人だな」というのが正直な感想でした。「臆病な自尊心」「尊大な羞恥心」という印象的なワードが代表するように、自分自身に対するプライド、他の人の視線や評判に敏感な自我の主張が前面に見えていました。再読してみると、その印象はそのままですが、ほかにも詩作について、書くことについて非常に辛辣な訓戒が含まれていることに気づきました。今日はそんな視点から、少しノスタルジックに。
隴西 の李徴 は博学才穎 、天宝の末年、若くして名を虎榜 に連ね、ついで江南尉 に補せられたが、性、狷介 、自 ら恃 むところ頗 る厚く、賤吏 に甘んずるを潔 しとしなかった。いくばくもなく官を退いた後は、故山 、に 略
帰臥 し、人と交 を絶って、ひたすら詩作に耽 った。下吏となって長く膝 を俗悪な大官の前に屈するよりは、詩家としての名を死後百年に遺 そうとしたのである。
李徴は若くして科挙に及第して官吏に登用された。自信家であり、下級官僚に留まって俗悪な上司の前にひざまずくよりは、詩人として名声を百年先にも遺すことを選んだ。「狷介」は「自分の意志を曲げず、人と和合しないこと」、「自ら恃むところ頗る厚く」は「自分の能力に過剰な自信を持っていること」。李徴は器用だったのだろうし、それを裏付ける成果も数多くあったのだと思います。詩作にもそれなりの自信があったから,「仕事つまらないし、漢詩で百年先に遺る作品と名誉でも打ち立てるか」なんて思った。

そんな李徴は虎に姿を変えてしまった。幸運にも旧友の袁傪に巡り合いましたが、次第に理性は薄れゆき、遠くない未来に心までも虎と化してしまうことを自覚しています。李徴は袁傪に、自作の詩を書きとってくれるよう懇願します。
他でもない。自分は元来詩人として名を成す積りでいた。しかも、業
未 だ成らざるに、この運命に立至った。曾て作るところの詩数百篇 、固 より、まだ世に行われておらぬ。遺稿の所在も最早 判らなくなっていよう。ところで、その中、今も尚 記誦 せるものが数十ある。これを我が為 に伝録して戴 きたいのだ。何も、これに仍 って一人前の詩人面 をしたいのではない。作の巧拙は知らず、とにかく、産を破り心を狂わせてまで自分が生涯 それに執着したところのものを、一部なりとも後代に伝えないでは、死んでも死に切れないのだ。
次の引用は前の部分に続くところです。
袁
は部下に命じ、筆を執って叢中の声に
随 って書きとらせた。李徴の声は叢の中から朗々と響いた。長短凡 そ三十篇、格調高雅、意趣卓逸、一読して作者の才の非凡を思わせるものばかりである。しかし、袁は感嘆しながらも
漠然 と次のように感じていた。成程 、作者の素質が第一流に属するものであることは疑いない。しかし、このままでは、第一流の作品となるのには、何処 か(非常に微妙な点に於 て)欠けるところがあるのではないか、と。
李徴にとって数少ない腹心の友であった袁傪の、素朴な感想が鋭く刺さってきます。「執着した詩を少しでも後世に伝えなければ、死んでも死にきれない」と愬(うった)える李徴に対し、どこか醒めた思考で「なるほど一流の部類なのだろうが、第一流になるにはどこか少し足りない」と。虎に身を墜とした今になっても、自らの運命や才能に酔っている李徴に対して、作品の真価を見極める冷徹な時代の目がそこに存在する気がします。袁傪がどんなに広く李徴の詩を喧伝したところで、彼の作品が百年の先に遺ることはないでしょう。

怖いのが、作家・中島敦がこの文言を記していること。書き手として、作品が時代や歴史の淘汰に耐えないというのは、恐ろしい考えなのだと思います。なぜなら、それは命や情熱を注いで書き上げた作品が無に帰してしまうのと同義だから。袁傪の素朴な声は作家が最も聞きたくない感想であり、それを敢えて言わせた中島敦の執筆に向き合う姿勢の厳しさ、プロ意識のようなものが伝わる気がします。同時に、「名誉を得ようという下心では、真に優れた作品は残せない」という戒めも含まれているのかもしれません。こうして見ると、学生時代になんとなく習った『山月記』の新たな一面が見られるのではないでしょうか。
作家と名誉について言うと、もう一つ思い出す文章があります。こちらも実は、高校の英語教材で取り上げられていたもので、The Chicken Soup for the Soul (邦題:心のチキンスープ)というシリーズから、The Shadowland of Dreamsという一篇です。アメリカでチキンスープは風をひた時に飲む定番の栄養食。心の栄養になるような、ほっこり温まる話や人との出会い、成功体験にかんする短編を多数の著者が寄稿する形で掲載されています。今回紹介するThe Shadowland of Dreamsは、翻訳するなれば「夢の裏通り」というところ。作者はAlex Haleyというアメリカ人の作家で、自らの家族からアメリカ先住民につながる起源を綴ったルーツという壮大な作品で知られています。
ヘイリーはもともと海岸警備の仕事をしていたのが、作家業に専念したいと思い退職。古いタイプライターしかない部屋で一人、孤独に執筆を書きはじめます。のちにアメリカで一世を風靡する作品でピューリッツァー賞を受賞した著者の、原点ともいうべき経験が記されています。(日本語版が手に入らなかったので、拙訳を添えて。)
Many a young person tells me he wants to be a writer. I always encourage such people, but I also explain that there’s a big difference between “being a writer” and writing. In most cases these individuals are dreaming of wealth and fame, not the long hours alone at a typewriter. “You’ve got to want to write,” I say to them, “not want to be a writer.” The reality is that writing is a lonely, private and poor-paying affair. For every writer kissed by fortune there are thousands more whose longing is never requited. Even those who succeed often know long periods of neglect and poverty. I did.
多くの若者が「作家になりたい」と言ってくる。彼らを私は応援するが、同時に「作家になる」ことと「書くこと」は違うのだと、言って聞かせることを忘れない。多くの場合、彼らが想像しているのは富や名声であって、一人きりでタイプライターに長時間向き合うことではない。「『作家になりたい』じゃなくて、『書きたい』じゃなければだめだ」。実際の執筆は、孤独で個人的で実入りの悪い作業だ。幸運に恵まれた作家が一人いるとすれば、その背後には報われなかった作家が何千人もいる。成功を掴んだ者の多くも、貧しく誰にも顧みられない長い下積みの期間を経験しているのだ。私がそうであったように。
「作家になりたい」ではなく、「書きたい」でなければならない。そのストレートなメッセージが、実感の重みをともなって刻まれています。作家は手を汚さずに富や名声を手に入れられる甘い稼業ではなく、生活や安定を擲(なげう)ってでも「書きたい」という切望のもとに、運がよければチャンスがついてくるというものなのだろうと思います。なかなか結果を出せず、友達に立て替えてもらった支払いが返せなくなる中、ヘイリーに海上警備の仕事が舞い込みます。年に6000ドルを見込める、立派な職場です。
Six thousand a year! That was real money in 1960. I could get a nice apartment, a used car, pay off debts and maybe save a little something. What’s more, I could write on the side. As the dollars were dancing in my head, something cleared my senses. From deep inside a bull-headed resolution welled up. I had dreamed of being a writer—full time. And that’s what I was going to be. “Thanks, but no,” I heard myself saying. “I’m going to stick it out and write.”
年収6000ドル!1960年当時、それは大した金額だった。きれいなアパートを借り、中古車を買い、借金を返してもまだ手持が残るかもしれない。それに仕事の傍ら執筆もできるのだ。ドル札が脳内を舞うのを感じながら、何かが違うと感覚が訴えていた。心の奥から頑なな意志が湧き上がった。私はフルタイムの作家になることを夢見ていたのだ。そしてそうなると決めたのだ。「ありがとう、でもやめておく」と答えている自分がいた。「粘って書き続けることにするよ」。
せっかくの仕事案件を棒に振ってしまったヘイリー。他の人には無謀で状況を顧みない判断に思えるけれど、「書きたい」という強い思いに突き動かされ、執筆の永く暗い道のりに戻ります。「書きたい」という望みにある意味翻弄される、作家の性を垣間見る気がします。
さて、虎から始まった今日の記事ですが、終わりは竜にしたいと思います。

小林秀雄の『文学と自分』という短い文章から。1940年、太平洋戦争へ向かう日本の「文学銃後運動」と名のついた会での講演記録です。「文学者は、戦にどう処するか」と問われ「銃を取る時が来たらさっさと文学など廃棄してしまえばよい」と答える小林の、芯まで突き詰めた「文学者の覚悟」が熱い文体で語られます。文庫本でニ十ページに満たない文章なので、要点なんていうものを稚拙に抽出するよりも、原文を読んでいただくのが一番です。その中から、わたしの好きな一節。
文学に志す人は、誰でも頭のなかに竜を一匹ずつ持って始めるものですが、文学者としての覚悟が定まるとは、この竜を完全に殺してしまったという自覚に他なるまいと考えます。ぼくの貧弱な経験から考えても、この仕事では口で言うほどたやすいものではなく、どうすれば殺せるかというわかりやすい方法があるわけでもない。これは単に思索の上の工夫ではなく、意志や感情や感覚による工夫でもあるからです。殺そうと思って帰って相手を肥らせるというようなことにもなりましょうし、忘れているうちに相手が死んでいるというようなうまいことにならぬともかぎらぬし、まあ要するに相手は魔性であると思えばまちがいない。
頭の中の竜を殺すということ。竜は名声への欲望でもあるだろうし、観念だけの空虚な文学論でもあるかもしれない。わたしの冗長な説明で覆いつくせるものではないですが、それを殺すということ、それが文学者の覚悟につながるというのです。
竜をうまく殺そうと思っているうちは駄目かもしれない。まず「書く」ということに真摯に向き合わなければ、良い文学は生まれないのだと思います。今日も読んでくださってありがとうございました。

※今回は高校の教科書に載っていた文章を取り上げましたが、ほかにも紹介してほしい作品などあれば、コメントなどお願いします!
#11 武士道からグローバリズムを考える~『武士道』/『新渡戸稲造はなぜ「武士道」を書いたのか』

オリンピック・パラリンピックが終わりました。多くの選手が活躍し、わたしも勇気や希望をもらいました。その一方で開催に向けての不祥事や懸念が相次ぎ、もやもやが多かったのも確か。特にせっかく日本の特色や文化を発信する場であった開会式・閉会式の演出にも影響が出てしまったことは、残念だと感じています。
オリンピック閉会式に、昼下がりの公園で着物でけん玉や縄跳びをして遊ぶ人たちを表現した一幕がありました。華やかで楽しい演出ではありましたが、強い違和感を感じてしまいました。確かに伝統的なものの組み合わせではあるけれど、現代人は今いちその価値を身をもって感じているわけではないし、「これが日本です」と対外的に発信したいかと言われると、なんか違う気がする。日本独特の感性とか、伝統の遊びとか、形ばかりでちょっと胡散臭いなあと思っていたところが、いよいよフジヤマ芸者的な、ショーケース用の取り合わせに変化している気がして。今日はちょっと辛辣。
そんな中、今日取り上げたいのは新渡戸稲造の『武士道』。原文は英語で書かれているので、正確には『Bushido』。なぜこの本なのかというと「世界の中での日本人のありかたについて、ヒントをくれるから」。ビジュアル対訳版というものを見つけたので、今回はこの本を軸に読み進めたいと思います。
奈良本辰也訳の『ビジュアル版 対訳 武士道』。他にはマンガ版や英語を学べるCD付きのものもあるそうです。こちらもリンクを貼っておきます。
新渡戸稲造(1862-1933)は盛岡出身の教育者・思想家で、農業経済学などにも精通した人です。東京大学に入学したものの尊敬できる教授や学びがないと幻滅して渡米、学びを深め、後にヨーロッパへ渡り国際連盟の事務次長もつとめました。
彼は序文に、この本を書いたきっかけとして、あるベルギーの著名な法学者と宗教について話した時の印象的な発見を記しています。
"Do you mean to say", asked the venerable professor, "that you have no religious instruction in your schools?" On my replying in the negative, he suddenly halted in astonishment, and in a voice which I shall not easily forget, he repeated "No religion! How do you impart moral education?"
The question stunned me at the time. I could give no ready answer., for the moral precepts I learned in my childhood days were not given in schools,; and not until I began to analyse the different elements that formed my notions of right and wrong, did I find that it was Bushido that breathed them into my nostrils.
「あなたがたの学校では宗教教育というものがない、とおっしゃるのですか」とこの高名な学者がたずねられた。私が、「ありません」という返事をすると、氏は驚きのあまり突然歩みをとめられた。そして容易に忘れがたい声で、「宗教がないとは。いったいあなたがたはどのようにして子孫に道徳教育を授けるのですか」と繰り返された。
そのとき、私はその質問にがく然とした。そして即答できなかった。なぜなら私が幼いころ学んだ人の倫たる教訓は、学校でうけたものではなかったからだ。そこで私に善悪の観念をつくりださせたさまざまな要素を分析してみると、そのような観念を吹きこんだものは武士道であったことにようやく思い当たった。

新渡戸稲造は日本文学や封建的な考え方に親しんでいた一方、16歳で入信した敬虔なクリスチャンでもありました。だからこそこの教授の指摘にははっとさせられたのだと思います。
前半では武士道の起源をたどる道筋として「仏教」から始まり、最高の支柱である「義」、人の上に立つ者の徳「仁」、苦痛と試練に耐えるための「名誉」が語られます。書き口で印象的なのは、新渡戸が日本人を「彼ら(they)」、西洋を「私たち(we)」と記していること。外国で長く暮らし、アメリカ人の妻を持ち、国際機関という世界を見渡す地平で働いた新渡戸が「外から日本を見る」視点で書いていることがうかがえます。
新渡戸の英語は正統、端正でクラシカルといった印象です。ヨーロッパやアメリカの読者層の背景知識を共有しているため、教養を感じさせる言い回しが多用されています。例えば最初の引用の「(善悪の認識などを)吹きこむ」に対応する「breathe in the nostrils(鼻腔から吹き込む)」は、旧約聖書でアダムに神が鼻腔から命を吹き込んだことに由来しています。遊び心や緩急の使いわけに富んだ岡倉天心の英語と比べると面白いと思います(ぜひ#9 『茶の本』の回を見返してみてください!)。

Courtesy and urbanity of manners have been noticed by every foreign tourist as a marked Japanese trait. Politeness is a poor vice, if it is actuated only by a fear of offending good taste, where it should be the outward manifestation of a sympathetic regard for the feeling of others. (中略) It means, in other words, that by constant exercise in correct manners, one brings all the parts and faculties of his body into perfect order and into such harmony with itself and its environment as to express the mastery of spirit over the flesh.
外国人旅行者は誰でも、日本人の礼儀正しさと品性の良いことに気づいている。品性の良さをそこないたくない、という心配をもとに礼が実践されるとすれば、これは貧弱な徳行である。だが礼とは、他人の気持ちに対する思いやりを目に見える形で表現することである。(中略)それはいいかえれば、正しい作法に基づいた日々の絶えざる鍛錬によって、身体のあらゆる部分と機能に申し分のない秩序を授け、かつ身体を環境に調和させて精神の制御が身体中にいきわたるようにすることを意味する。
「日本人の礼儀正しさ」について。表面だけ愛想よく、波風を立てないように行動するように見える「礼」の議論についても、西洋の議論の様式に則って、その起源と価値を説明しています。他の部分では、「武士団が高次元な道徳を生みだせるのか」という問いに対して、「西欧の騎士道と同じように、壮大な倫理体系を打ち立てるかなめ石の上に立っているのだ」と返します。強固な論と熱意と、説得力を添える修辞法が見事だなと思います。
『武士道』の後半では、武士道が追求した「大和魂」が日本人に広く根付いた理由や、明治時代に入り「遺産」へと変化してきた武士道がこの先どのように受け継がれのかについて語られます。

さてここで、「元祖・グローバルに活躍した日本人」新渡戸の意図や思いに焦点を移し、草原克豪著『新渡戸稲造はなぜ「武士道」を書いたのか』という一冊を開いてみたいと思います。この本には、国際連盟脱退などについての新渡戸の見解も記されており、彼の思想や働きを筋だって知るのに良い一冊だと思います。
これまでの語り口から、新渡戸が日本の宗教・文化・社会についての深い素養を持ちながら、世界の平和や繁栄のために尽くした人だと感じられたところと思います。
一般的な新渡戸像とは、人格を重視した教育者であり、敬虔なクリスチャンであり、平和を追求した国際人といったものであろう。それはそれで間違いではない。しかし、そこには大事な側面が書けているのだ。それは、彼が人一倍熱い愛国心の持ち主であったという事実である。(中略)新渡戸や世界的視野を持った愛国者として、常に日本の繁栄を考え、日米の友好親善、世界平和の実現を目指して発信し続けた。
新渡戸は学生たちに、自分の世界に閉じこもった「虫の目」よりも、俯瞰的な「鳥の目」を鍛えることが重要になると説きました。
このことを新渡戸は、「センモンセンスよりもコモンセンス」という言い方で学生に伝えた。そして、自分だけの狭い世界に閉じこもらず、広く人と付き合い、社会に交わることが大事だと説いた。そのためには、異分野・異文化の人たちとのコミュニケーション能力を高めることが重要になってくる。ただし、コミュニケーションとは単なる技術ではない。問題は何を話すか、その中身であり、思想である。
新渡戸は二項対立的な物の見方を好まず、物事の関係性から共通点を見出す「中庸」の考え方を支持したといいます。多様性に満ち、白黒つけがたい問題が増えた現代、全体を俯瞰したうえで物事の本質にせまるバランス感覚が重要だ、と草原氏は指摘します。さらに、現在世界を舞台に活躍する日本人には、日本の感性や文化の特徴を生かして活動する人が多いことを挙げて、こうも言っています。
こうした事例は、それぞれの国や地域が長い歴史の中で築きあげてきたローカルなものにこそ真の文化的価値が宿っていることを示している。ローカルなものなしには、グローバルな価値も生まれないのである。言い換えれば、グローバル化時代だからこそ、ローカルななものの価値を大事にしなければならないのだ。
詭弁のようだけれど、グローバリズムの進んだ世の中で求められるのはローカルな価値だということ。それなら、「個人レベルのグローバリズム」は、それぞれの人が自分の起源や来歴を土台に、対等な関係で世界の課題に取り組めることなんじゃないかと感じます。そのためには、身体ひとつで異国や異文化へ飛び込んで行ったとしても、わたしを内側から支える「日本」を、連れて歩けるようにしたいと思う今日この頃です。
~今日のおまけ
実はまだ、読んでいないのだけれど…。自分のアイデンティティや起源と向き合い、他人の人生の背景を尊重し、折り合えなければ衝突することもある。なんだかんだ多様性の少ない日本では実際に出くわすことの少ない、生の多様性の体験みたいなもの。読書の秋に読んでみたいなと思っています。

![華麗なるギャツビー [Blu-ray] 華麗なるギャツビー [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51-iEzq7kML._SL500_.jpg)
![華麗なるギャツビー [Blu-ray] 華麗なるギャツビー [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/61Gnzp1pddL._SL500_.jpg)






















